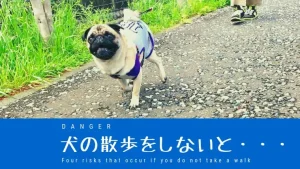しげおパパ
しげおパパ先日、犬の散歩をしないことで起こるリスクについてお話ししました。
今日はその中のひとつ「肥満」を掘り下げていきたいと思います。
人間の肥満というのは、さまざまな病気のリスクを高めると言われています。
これは犬にも言えることで、犬も肥満になってしまうとさまざまな病気のリスクが高まります。
ここでは、具体的にどのような病気のリスクが高まるのか、飼い主はどう対策をすべきなのかについてご紹介していきたいと思います。
犬の肥満で高まる病気のリスクとは?

犬の肥満で高まる病気のリスクとしては、まず体重増加による関節炎や椎間板ヘルニアといったものが挙げられます。
これは単純に体重の増加によって、関節や骨に負担がかかってしまうことによって起こります。
また、脂肪が増えることによって呼吸器系の病気や皮膚炎、便秘といったものリスクが高まると言われています。
呼吸器系の病気は脂肪によって気道が圧迫されることによって起こりますし、同じように腸が圧迫されることによって便秘が引き起こされます。
皮膚炎と脂肪はあまり関係がないように思えるでしょうが、皮下脂肪の増加によって皮膚がたるんでしまうとそのたるみのところで皮膚炎が起こりやすくなるのです。
そして、人間と同じように糖尿病のリスクも高まります。
糖分の過剰摂取によって、インスリンの働きが鈍くなり、血糖値が高い状態になってしまうのです。
糖尿病単体でも恐ろしいのですが、糖尿病によって引き起こされる合併症のリスクも忘れてはいけません。
飼い主ができる対策とは?

食事の量
飼い主にできる対策としては、まず食事の量の調節です。
基本的に犬は与えられれば与えられた分だけ食べようとします。
そのため、栄養バランスはもちろん、食べさせる量も飼い主の方がしっかりと考えていかなければいけません。
毎日の散歩
また、運動不足からの肥満にならないように毎日の散歩も一緒におこなうようにしましょう。
散歩は運動不足を解消させるだけではなく、ストレス発散にもなりますので、肥満対策も兼ねて毎日おこなっていきたいものです。
こういった食事や散歩での対策をしながら、こまめに愛犬の体重をチェックすることも大切です。
犬の体重の考え方
ちなみに、犬の体重の考え方ですが「愛犬の普段の体重の何分の1の増減なのか?」と考えることで、人に換算するとどのくらいの増減なのかが分かります。
 しげおパパ
しげおパパもしも自分の体重が3kgも増えていたら、たった3kgとは言えませんね。
まとめ

このように人間にとっては微々たる増量であっても、もともとの体の大きさが違う犬にとっては大きな変化となります。
体重や愛犬の見た目などからも判断していきましょう。
今では、スマホで簡単に愛犬の体重管理、健康管理ができるアプリが多数ありとても便利です。