 しげおパパ
しげおパパ『てんかん』というと人間がかかるものというイメージがあるかと思いますが、実は犬は人間以上にてんかんになりやすい傾向にあります。
そして犬のてんかん発作は突然発生するものです。
もしも飼っている愛犬がてんかん発作を起こしても慌てず対処するにはどうしたらいいでしょう。
ここではそのてんかんの症状、原因、対処法などについてお話ししていきたいと思います。
犬のてんかんの症状

犬のてんかんの症状としては、びくびくと痙攣を起こす、強く固まった状態になるといったものが挙げられます。
手足や顔面など全身で痙攣を起こす可能性がありますし、失禁をするといったこともありますが、これらはまだ軽い症状になります。
重い症状になると、体を反らしたり、その状態で口から泡を吹いたり、意識を失ったりといったことが起こります。
ただ、重い症状であったとしても2分から3分ほどで何事もなかったかのように症状が消えてしまうこともあります。
犬のてんかんの原因

人間の体には体の隅々にまで神経が張り巡らされています。
その神経の中には電気信号が通っており、それによってさまざまな情報が伝達されるのです。
こういった部分は人間も犬も同じです。
人間にとっても犬にとっても重要な部位である脳には、たくさんの神経細胞が集まっています。
ここでも電気信号の伝達がおこなわれているのですが、これがショートしてしまうことがあります。
それによって起こるのがてんかんの発作なのです。
なぜショートしてしまうのかというと、大きくわけて3つの原因が考えられます。
病気

例えば、脳腫瘍などの脳の病気からてんかんが引き起こされるケースというのは少なくありません。
脳の病気以外にも、感染症や炎症などによっててんかんが引き起こされることもあるのです。
遺伝

まだ遺伝子の特定はされていないかと思うのですが、遺伝によっててんかんとなってしまうこともあります。
実際に、犬種によっててんかんになりやすいかどうかは違ってきます。
環境

例えば、農薬など有害なものを犬が口にしてしまったためにてんかんとなってしまうこともあります。
何でも口に入れてしまう犬だからこそ、飼い主の方がその環境に気を付けなければいけません。
ただ、中には本当に原因がわからずにてんかんとなってしまうこともあります。
その原因が必ずしも明確になるわけではないのです。
犬のてんかんの対処法

飼い主の方にとって愛犬のてんかん発作というのはショッキングです。
しかしながら、慌てて対処するのはいけません。
てんかん発作が起こったときの対処法も頭の中に入れておきましょう。
- 体を揺すらない、抑えない
- 周りにあるものをどかす
- 犬の様子を記録
体を揺すらない、抑えない
まず、体をゆすったり、無理やり押さえたりしないことです。
特に、口の中には触れないようにしておきましょう。
発作の最中は飼い主の手であっても混乱して噛みついてしまう危険があります。
てんかん発作を起こしている犬の力は尋常ではありません。
飼い主の方が怪我をしてしまう可能性もありますし、犬が怪我をしてしまう可能性もあります。
周りにあるものをどかす
また、犬の周りに危険なものがないかを確認しておきましょう。
犬を移動させるのではなく、犬の周りにある危険なものを遠ざける形で動いていきましょう。
ぶつかったり落ちてきたりすることによって怪我をする可能性のあるものは、すべて遠ざけておきたいものです。
犬の様子を記録
そして、犬の様子をよく見ておくことです。
可能であればスマホで動画を撮っておくことをお勧めします。
「てんかんの発作が起こっているのに見てるだけ?動画を撮る?」と思うかもしれませんが、その後、病院に連れていくことを考えたらどのような様子であったのかを見たり記録したりすることはとても大切です。
治療方針にもかかわってくる部分ですので、よく見ておきましょう。
この時、撮った動画があれば病院の先生にもその時の様子が伝わりやすいです。
犬のてんかんの治療法
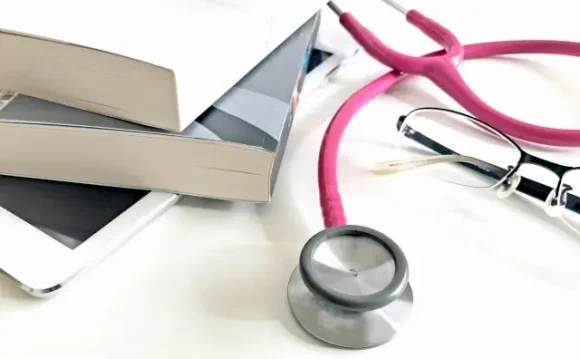
犬のてんかんの治療法についてですが、基本的には抗てんかん薬による治療が中心となってきます。
抗てんかん薬はてんかんの治療をするものというよりは、発作の回数を減らしたり、発作の症状を軽くしたりすることを目的としています。
場合によっては、一生飲み続ける可能性もあります。
もちろん、他の病気からてんかんが起こっている場合には、その病気の治療をおこなっていくことになります。
まとめ

犬は人間以上にてんかんになりやすい生き物です。
てんかんと疑われる症状が出た場合は、まずは愛犬には触れず安全確保の為に周りにある危険な物をどかす。
そして診察の為に発作の回数や発作が続いた時間をメモしたり、発作の様子を動画に記録したりすることが大切です。
これらのことを発作が起こったときに慌てず落ち着いて行動することが重要です。






